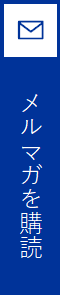コラムカテゴリー:DX(デジタル・トランスフォーメーション), ITコンサルティング, プロジェクトマネジメント, 情報戦略/業務改革
DXとデジタル化の違いを見極める3つの視点 〜経営者が押さえておくべき本質〜
「当社もDXを進めています」
経営者や役員の皆さまから、こうした言葉を耳にする機会が増えています。
しかし実態を冷静に見てみると、システムの一部をクラウド化する、紙の書類をPDFに変える、RPAで定型作業を自動化するなど、「デジタル化」レベルにとどまっているケースが少なくありません。
こうした取り組みも、短期的な業務効率化やコスト削減といった効果が期待できる改善策となり得ます。
その一方で、デジタルトランスフォーメーション(DX)では、将来の競争力を築くために、顧客への価値提供のあり方やビジネスモデルの再設計といった視点からの取り組みが求められます。
この視点で評価をした場合には、「DXの成果が出ていない」という状態であると言えます。
なぜこのような状態となるのか。
その背景には「目的が曖昧なままツールを導入する」「経営と現場の意識が噛み合わない」といった構造的なすれ違いが存在します。
そこで本コラムでは、「DXとデジタル化は何がどう違うのか」をあらためて整理し、DXとして成果を出すために経営者として押さえておくべき3つの判断軸(視点)を提示します。
- 視点①:目的の違い(効率化か、変革か)
- 視点②:取り組み主体の違い(現場主導か、経営主導か)
- 視点③:成果の評価軸の違い(コスト削減か、新たな価値創出か)
これらを明確に区別することは、IT投資をコストで終わらせず、将来の競争力へと昇華させる鍵になると考えます。
貴社の現在の取り組みを改めて見つめ直すきっかけとして、本稿をお役立ていただければ幸いです。
記事の執筆

高橋 和大
ファシリテーション能力を強みとし、プロジェクトマネジメント・PMO支援を中心にコンサルタントとして活動している。 プロジェクトの円滑な推進を支援し、プロジェクトを成功に導いている。 上記のほか、大手通信販売業のデータベースマーケティング業務に従事し、販売高の向上に貢献した経験を持つ。 また、前職では経理業務に従事し、日々の出納業務から決算業務、予算編成、予算/管理などの業務経験を持つ。
視点①:目的の違い
最初の視点は、「何のために取り組むのか」という目的の違いです。
デジタル化の目的は、既存業務の効率化やミス削減、コスト削減といった、いわば“現在の仕事をよりスムーズに進める”ことにあります。たとえば、紙の申請書類をPDFに置き換える、RPAを導入して定型的な入力作業を自動化する、といった取り組みがこれに該当します。
これらは、業務の無駄を省き、限られたリソースで高いパフォーマンスを発揮するためには非常に有効です。
一方で、DXが目指すのは、将来の持続的な成長や競争力強化といった中長期的な経営課題の解決です。
そのために、顧客への価値提供の方法や自社のビジネスモデルそのものを見直し、必要に応じて再構築することがDXの中核的な取り組みになります。たとえば、これまでリアル店舗での販売を主軸としていた企業が、アプリを中心としたサービスに転換し、定期課金型(サブスクリプション)で顧客と長期的に関係を築くビジネスに変革する。これがDXの代表例です。
つまり、デジタル化は現在の業務の延長線上にある「最適化」を目的としますが、DXはその先にある「持続的な企業成長、競争力の強化などを見据えた変革」を目的としており、その一環としてビジネスモデルなどの変革に取り組むことが必要になると言えるでしょう。
視点①目的の違いを端的に表現すると以下のとおりです。
「業務を楽にする」のがデジタル化。
「将来の成長、競争力強化などを見据えて変革に取り組む」のがDX。
視点②:取り組み主体の違い
2つ目の視点は、「誰が主導して進めるのか」という取り組み主体の違いです。
デジタル化の取り組みは、多くの場合、IT部門や現場の業務部門が中心となって進められます。
たとえば、経理部門が請求書処理の電子化を進めたり、営業部門がSFA(営業支援ツール)を導入して活動の記録をデジタル化するといったように、各部門ごとの課題に対応する形で局所的・限定的に実施されるケースが一般的です。
このような現場主導の取り組みは、部門内の効率化には効果を発揮しますが、ビジネスモデルの変革には直結しにくい傾向があります。
一方で、DXでは企業として将来の競争力を見据えた方向性や価値創出のあり方をあらためて捉え直す必要があります。
たとえば顧客接点の再設計や新たな提供サービスの構築などを通じてビジネスモデルの変革につながっていきます。
こうした大きな変革を進めるには、なぜその変革に取り組むのかという経営層の意図を明確にし、組織全体でビジョンを共有することが重要です。
たとえば、「これまでのビジネスモデルでは5年後に市場で勝てない。だからこそ、全社的に顧客接点を再構築する」など。
トップが変革の意図を明確に語り、組織全体を巻き込んでいく姿勢が求められます。
視点②取り組み主体の違いを端的に表現すると以下のとおりです
「現場で取り組む」のがデジタル化。
「経営主導で方向性を示し、全社的に推進する」のがDX。
視点③:成果の評価軸の違い
3つ目の視点は、「成果をどう評価するか」という評価軸の違いです。
まず前提として、デジタル化であってもDXであっても、最終的には定量的な指標で成果が評価されることに変わりはありません。重要なのは、その取り組みにおいて「何を成果と見なすか」「何に重きを置いて評価するか」の違いにあります。
デジタル化の主な評価軸は、業務効率やコスト削減です。たとえば以下のような指標が用いられます。
- 業務工数の削減率(例:処理時間30%短縮)
- 人件費・外注費の削減額
- エラー件数の削減
- ROI(投資回収率)=(効果−投資額)÷投資額
これらは定量的に評価されますが、実際には「作業が楽になった」「現場の負荷が軽減された」など、定性的な評価もあわせて行われるのが実情です。
一方で、DXにおいては“新たな価値の創出”という視点から成果を評価することが求められます。
ここでいう「価値」とは曖昧な概念ではなく、新たな売上、顧客体験の改善、競争力の強化といった、定量で測れる成果指標のことです。
具体的な評価指標の例としては以下のようなものがあります。
- 新規事業の売上高・構成比
- 新サービスの市場投入後の収益化までの期間(単黒到達時期)
- NPS(Net Promoter Score)などの顧客満足指標
- アプリやWeb、リアル店舗での購買行動などのLTV(顧客生涯価値)
- マーケットシェアの拡大
- リカーリング(継続)収益の成長率
視点③成果の評価軸の違いを端的に表現すると以下のとおりです。
「業務がどれだけ楽になったか・効率化されたか」を評価するのがデジタル化。
「将来の成長、競争力強化を見据え、どのような価値を新たに生み出したか」を評価するのがDX。
まとめ:本質を押さえ、DXを成果につなげるために
ここまで、DXとデジタル化の違いを3つの視点から見てきました。
|
視点 |
デジタル化 |
DX(デジタルトランスフォーメーション) |
|
①目的の違い |
業務を楽にする |
将来の成長、競争力強化などを見据えて変革に取り組む |
|
②取り組み主体の違い |
現場で取り組む |
経営主導で方向性を示し、全社的に推進する |
|
③成果の評価軸の違い |
業務がどれだけ楽になったか・効率化されたか |
将来の成長、競争力強化を見据え、どのような価値を新たに生み出したか |
この違いを正しく見極めることは、今後のIT投資や変革施策を単なる「効率化の延長」にとどめず、企業の競争力を再定義する取り組みとして位置づける上で不可欠です。
まずは、自社の現在の取り組みが「デジタル化」なのか、「DX」なのか、その位置づけを客観的に捉えることが第一歩です。
さらに、DXを進めるうえでは、経営の意図を具体的な行動へと落とし込み、現場の共感と自発性を引き出す取り組みが必要です。たとえば、小さな成功事例を部門間で共有したり、現場の声を拾い上げて改善に反映したり、経営層のメッセージを現場まで浸透させる草の根活動と言われるような取り組みが有効です。
DXに取り組む経営者様へ
「DXをやっている」この言葉だけでは、もはや十分ではありません。
本当に問われるべきは、「DXを通じて、何を変えたいのか」という経営としての意思です。
デジタル化はDXの実現に向けた重要なステップであり、業務の効率化や基盤整備を通じて、変革の足場を築くものです。そのためDXと混同されやすい部分があることも事実です。しかし、DXとはその延長線上に自然と存在するものではなく、企業として目指す将来像に向けて、自社のビジネスモデルや価値提供のあり方を根本から見直す取り組みです。
現場任せではなく、トップマネジメントが方向性と覚悟を示し、組織を導いていく。
そのためには、DXの本質を正しく理解し、自社の現在地を客観的に見つめ直すことから始まります。
これからの経営において、「変革に向き合う姿勢そのもの」が企業価値そのものになる時代です。
ぜひこの機会に、貴社のDXの取り組みを、経営の目線で再点検してみてはいかがでしょうか。
関連サービス
2025年07月22日 (火)
青山システムコンサルティング株式会社