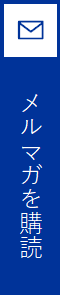コラムカテゴリー:DX(デジタル・トランスフォーメーション), その他
記事の執筆

マネジャー吉田 勝晃
業務改善を得意とし、ITを活用して企業を強化・効率化するコンサルティングを強みとする。 また、公共機関の業務改善を行った実績も多く、公共機関向けのコンサルティングでも豊富な実績をもつ。
近年、「人間の行動」を心理学と経済学から分析する「行動経済学」が注目されています。
以前、ITコンサルタントのつぶやき「今こそ「行動経済学」を」で行動経済学を簡単に紹介しましたが、今回はもう少し詳しく紹介したいと思います。
行動経済学とは
行動経済学は「経済学」に「心理学」を組み合わせて、人間の行動のメカニズムを分析する学問です。
ベースとなる「経済学」の定義は経済学者により多様ですが、行動経済学における経済学は「経済活動(モノ、カネ、サービスなどの流れ)における人間の行動」の分析です。
この定義を見るとそのまま行動経済学の定義となりそうですね。
ではなぜ経済学とは別に行動経済学が生まれたのか。
経済学では「人間は合理的な意思決定を行い、常に利益を最大化するように行動する」ことを前提としています。
しかし、実際には人間が常に合理的な行動をすることはなく、頻繁に非合理な行動をしてしまいます。
行動経済学は、この「非合理」を心理学視点で考慮し、「人間は非合理な行動をする」ことを前提に人間の行動を分析した学問です。
行動経済学をビジネス活用するための代表的な理論
行動経済学は様々な分野の理論が関わっています。
今こそ「行動経済学」を(ITコンサルタントのつぶやき)では「バンドワゴン効果」と「ナッジ理論」に触れましたが、ビジネス活用に効果的な理論として、「システム1・システム2」「プロスペクト理論」「フレーミング効果」も紹介します。
ITコンサルタントのつぶやきで紹介した理論も含めて、行動経済学は多くの理論で構成されていますが、これらの理論に明確な相関関係がある訳ではありません。紹介する理論も含めて、複数の理論で人間の行動を分析しているため、1つ1つの理論を理解しておくことが活用の幅を広げます。
システム1(直感)・システム2(論理)
ダニエル・カーネマン氏(行動経済学者)の著作「ファスト&スロー」で広く知られることになったこの理論ですが、行動経済学においては不可欠な理論です。
同書では、人間が行動の意思決定を行う際、以下の2種類を使い分けているとしています。
- 自動的に高速で働き、努力はまったく不要か、必要であってもわずかである。また、自分のほうからコントロールしている感覚は一切ない。
(システム1:直感的な判断) - 複雑な計算など頭を使わなければできない困難な知的活動にしかるべき注意を割り当てる。
(システム2:熟考して論理的に判断)
代表的な例として、同書では以下の問題が掲載されています。
「バットとボールは合わせて1ドル10セントです。バットはボールより1ドル高いです。ボールはいくらでしょう?」
この問題に対して、すぐに「10セント」と答えが浮かんでしまう思考がシステム1です(答えは10セントではありません)。
このように、システム1は直感的で労力なく判断できますが、時として認知バイアス(思い込み等)により不合理な判断をしてしまう特徴があります。
対して、システム2は論理的に注意深く判断しようとする思考ですが、その思考にはより多くの労力を要するため、些細なことも含めてすべての物事をシステム2で判断していたら時間もかかる上に脳がバーストします。
ビジネスに活用する上で押さえておくべき点は、システム1とシステム2のどちらが優れているかではなく(実際にどちらも必要)、「システム1が思考のデフォルト」であることです。
システム2はシステム1で答えが出せない時に働くとされており、つまりは、システム2で判断させたい場合は、システム1で答えを出せない状況を意図して作り出す必要があるということです。
システム1で判断してしまいがちなケースとして、「情報量(選択肢)が多い場合」「見慣れている情報の場合」「時間がない場合」等があげられており、システム2で判断させたいケースでは、システム1に該当しない状況を作り出す必要があるということです。
プロスペクト理論・フレーミング効果
プロスペクト理論は、「人間は、不確実性がある状況では損失回避性(利益を得ることよりも損失を避ける)により合理的な価値判断ができない」という理論です。
この理論の例として、よくコインゲームがあげられます。
「表が出れば10万円貰える、裏が出れば3万円支払うコインゲームに参加する」か「コインゲームに参加しない場合は1万円貰える」の選択肢があった場合、人間は10万円というより大きな利益を得るチャンスよりも、3万円を失う可能性のリスクを優先させてしまい、確実得られる小さな利益を優先してしまう理論です。
実際、この質問をするとほとんどの人が「参加しない」を選択します。
プロスペクト理論をビジネスに活用する上では、フレーミング効果も知っておくとより有効です。
フレーミング効果は、同じ情報でも表現方法(フレーム)を変えることで、情報の受け取り方が変わり、意思決定が変わってしまう理論です。
例えば、「満足度90%」と「不満足度10%」はどちらも同じですが、何を強調するかで受け手の印象も変わり、意思決定に影響する理論です。
プロスペクト理論とフレーミング効果を活用した活用事例として、「期間限定の割引キャンペーン」があげられます。
さて、どちらのキャッチコピーがより人間の行動に影響を及ぼすでしょうか?
① 5月限定割引、今がお得!
② 5月限定割引、今買わないと損!
「期間限定の割引キャンペーン」そのものが「今買わないと損をするかもしれない」の心理を働かせていますが、この場合はフレーミング効果で「得」よりも「損」を強調する方がより損失回避性を強化できるので、②の方がより人間の行動を促進することになります。
行動経済学×ビジネス
当コラムやITコンサルタントのつぶやきで紹介した理論だけでなく、ビジネスに活用可能な行動経済学に含まれる理論は他にも沢山あります(ハロー効果、デコイ効果、プライミング効果 等)。
ビジネスのベースが「人間の行動」である以上、人間の行動のメカニズム分析は必要であり、行動経済学も人間の行動変革の一助となるはずです。
例えば、システム1の判断においてプロスペクト理論やデコイ効果(今回は紹介していませんが)は有効です。
逆に、システム2で熟考して判断して欲しいケースで、プロスペクト理論やフレーミング効果を狙って多すぎる情報量を提供してしまうと、システム2よりシステム1が優先されてしまいます。
人間の行動を体系的に整理することは簡単ではありません。
行動経済学でも沢山の理論を用いて人間の行動を整理しています。
ビジネス活用においては、これらの理論を上手く組み合わせて人間の行動に合った対策を行うことが重要です。
関連サービス
2025年05月13日 (火)
青山システムコンサルティング株式会社