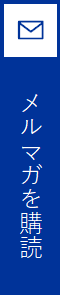弊社メールマガジンで配信した「コンサルタントのつぶやき」です。
IT利活用のトレンドやお役立ち情報をメールマガジンでお届けしています。
記事の執筆

システムコンサルタント柴田 将吾
システムの活用を通じて、業務の変革を支援したいという思いから、青山システムコンサルティングに入社。前職では、大手予備校にて、模擬試験のリモート受験サービスの立ち上げに従事し、要件定義からシステム導入、導入後の業務フロー整備まで一貫して主導した。
最近は株式市場が堅調な動きを見せ、投資に関する話題や情報が日々飛び交っています。そうした中でよく耳にするのが「投資は自己責任」という言葉です。これは、投資家が自らの判断で取引を行った以上、たとえ損失を被ったとしても、その結果は自らが負担するという原則です。つまり、銀行や証券会社などから助言を受けたとしても、最終的に「どこに・いくら投資するか」という判断と、その結果に対する責任は自分自身にあるという意味です。
この考え方は、企業におけるシステム導入にも通じるものがあります。システム導入は会社にとって大きな投資であり、導入の過程では多くのベンダーやコンサルから提案や助言が寄せられます。しかし、最終的な意思決定は、あくまで自社の判断で下さなければなりません。
近年、AIをはじめとする新技術が次々と登場し、システムに求められる役割も大きくかつ高度になりつつあると感じていますが、多くの企業では日々の業務に追われ、技術の進歩を十分に把握する余裕がないのが現状です。そうした中で「AIでイノベーションを起こしたい」「データドリブン経営を実現したい」といった大まかな方針を頼りにベンダーやコンサルのような外部に提案を求めるケースも少なくありません。
もちろん、自社にない知見を社外に求めること自体は悪いことではありません。外部の専門家は自社にない知識やアイデアを補ううえで有用です。ですが、これらのアイデアや提案はあくまで“外部の視点”であり、自社の制約条件や目的、期待値を完全に理解したうえでの提案とは限りません。外部の意見にはそれぞれの立場があり、ビジネス上の思惑やポジショントークによって過剰に期待を煽る内容が含まれる場合もあります。そのため、提案を受け取る側としても、正確な情報を精査するために質疑応答を通じて確認を行うことが重要です。
実際、「AI-OCRを導入すれば帳票入力が自動化できる」と期待したものの、帳票フォーマットの多様性や学習データ不足で精度が上がらず、手作業が残ったケースや、「AIによる需要予測で効率的な生産計画を立案できる」と謳われても、十分なデータ量が確保できず実用化に至らなかったケースも少なくありません。こうした期待と現実が乖離する事例は、現在の技術水準や前提とする条件などを十分に確認せず導入したことが原因であるケースも多いです。
このような事態を防ぐためにも、外部からの提案をただ待つだけでなく、「自社でも積極的に情報を集める」姿勢が重要だと考えます。世の中の一般的な技術水準を把握しておけば、提案内容の実現可能性や必要な前提条件がある程度想像がつきます。また、主要ベンダーの製品概要や導入事例を比較したり、成功事例と失敗事例を調べたりするだけでも、システム導入前に確認すべき事項の判断がつくようになります。
現在は幸いなことに、容易に情報を入手できる時代です。書籍や解説動画に加えて、ChatGPTやGeminiといった生成AIツールも、論点整理や多角的な視点の獲得において有効な手段となります。こうした比較的利害関係に左右されない中立的な情報収集を行い、意思決定に必要な知識を自社内に蓄積していくことが、システム導入という大きな投資を成功へと導く鍵になると考えます。
2025年10月20日 (月)
青山システムコンサルティング株式会社
柴田 将吾